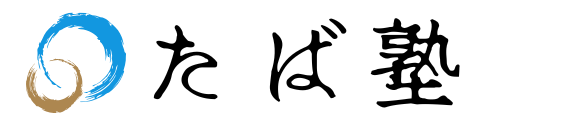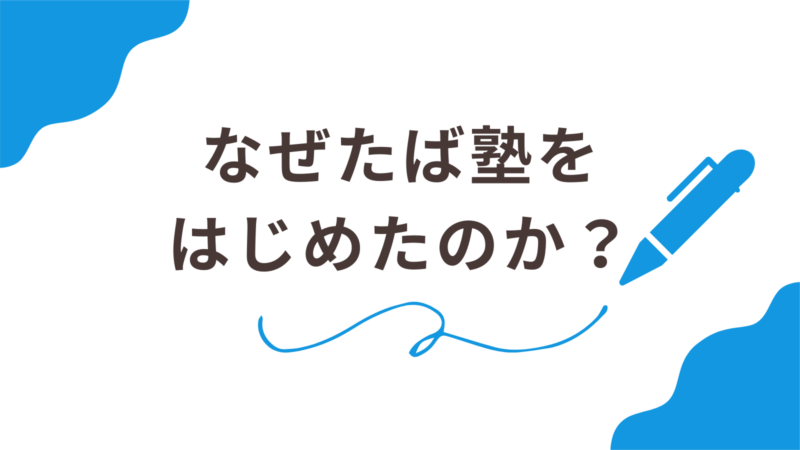なぜたば塾をはじめたのか?
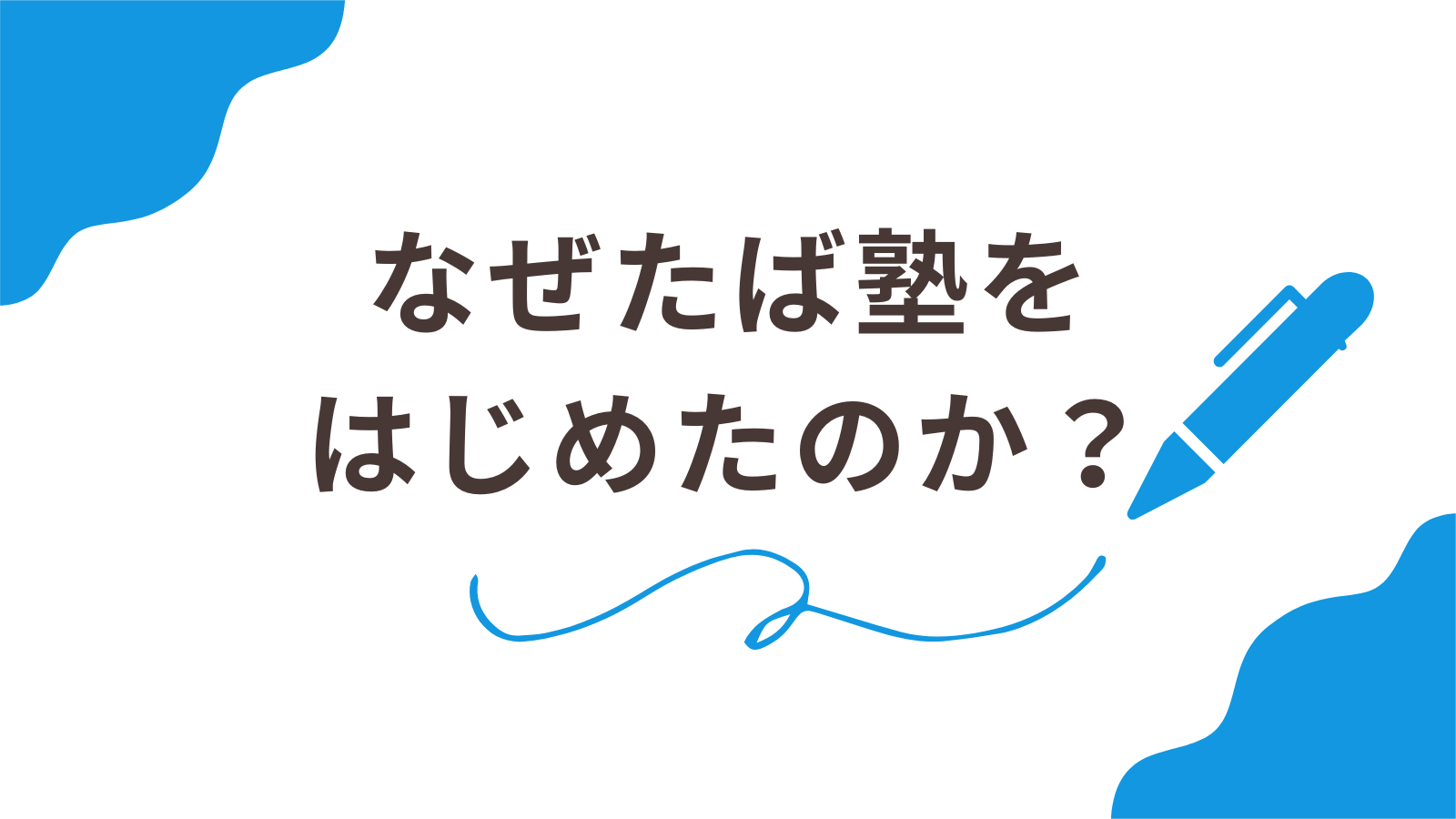
「学校に任せておけない。自分でやるしかない」
うちの長男は、小学校5年生の春から学校に行きづらくなりました。
集団行動が苦手で、みんなと同じことをやるのがとにかくしんどい。行進も歌も、本人にとっては苦痛だったんです。
最初は「まあ、そういう子もいるよな」と思って見守っていました。ところが5年生の秋から、教室に入れない日が増えてきた。6年生になると、ついに教室に入れなくなり、図書館登校になりました。
それでも「学校に行く意味」を一緒に考えたり、家でドリル学習をしたり、父としてできる限りサポートしてきました。
でも、6年生の春。学校から電話がありました。
「今すぐ来てください」と。私は「会社から1時間かかります」と伝えました。
そのとき、学校の先生が沈黙したんです。
「ああ、この人たちは、“親が仕事を辞めてでも来い”と言ってるんだな」と思いました。
本当にそう感じました。
その瞬間、心が決まりました。
「これはもう、学校に任せておけない。自分でやるしかない。」
子どもが苦しんでいるのに、大人はマニュアル通りの対応しかできない。
「暴力だから警察に行ってください。」
「支援級に行くしかない。」
そんな言葉ばかり。
これが今の教育現場のリアルなんです。
ずっと感じてきた、教育の限界
私はずっと、教育の限界を感じてきました。
大企業に勤めたときもそう。みんなが仕組みにハマって、「考えること」が減っていく。これは学校教育と同じ構造です。
学校の先生たちも大変です。教育の仕組みが古すぎて、先生が学び続ける仕組みがほとんどない。
「研修?評価?キャリアアップ?」そんなものはありません。
新人の先生でも、いきなりクラス40人を任される。誰にも教えてもらえない。だから、頑張る先生とそうじゃない先生の差がどんどん開いていく。これは構造の問題です。
プロ家庭教師として受験指導をしているときも、ずっと違和感がありました。
やっと勉強が楽しくなってきた子どもが、模試の偏差値や学校の成績で自信を失う。
「いや、それあなたの価値じゃないから。」
そう何度も伝えてきました。でも、失った自信が戻ることは、ほとんどありませんでした。
「子どもが自分の人生を、自分で決める力を育てたい。」
だから私は、たば塾を始めました。
「子どもが自分の人生を、自分で決める力を育てたい。」
その想いだけです。
私は自分の名前をつけました。かっこつけるつもりはありません。教育は、人と人の繋がりです。だから逃げられないように、自分の名前で勝負しています。
たば塾では、「好きなこと」から学びを始めます。
誰かに決められたカリキュラムじゃなく、自分で考え、自分で選び、自分で動く。
その中で、AIも活用するし、本人が希望すればドリルだってやります。でも、やらされる勉強はしません。
実感する、教えないことの難しさ
塾を始めて実感したのは、「教えないことの難しさ」です。
教えないからこそ、こっちが準備しないといけない。子どもが迷ったときのコンパスになる必要がある。これは今も試行錯誤しています。
でも、確信もあります。
小3の女の子が、家族について探求する2回目の授業でこう言いました。
「弟はきっと今日私が気づいたことに気づいてない。ってことは、私もまだ気づいてない私がいるんだと思う。それを知りたい。」
これが学びです。これが探究です。
—
たば塾に来る子どもたちには、「地平線を広げる人」になってほしい。
今より少しでも、世界を良くする人になってほしい。
どんな小さなことでも、自分が動けば世界は変わります。
私は、それを信じています。
最後に
最後に、伝えたいことがあります。
「比較の中で生きるのではなく、自分の人生を、自分で決めきる。」
私は、少なくとも自分の子どもにはそう育ってほしいと思っています。
そして、たば塾に来てくれる子どもたちにも、そう接していきます。
それが、私がたば塾を始めた理由です。